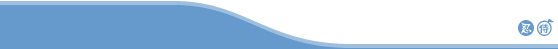今日は珍しく体の調子が良くて、3時間目まで普通に授業を受けていた。
いつもはどんなに体調が良くても、2時間目くらいから眩暈がしてきたり、薬の効果が切れてきて咳がひどくなり始めて保健室に行ってしまうのだけど。
教室に行って、保健室に行って、ベッドで寝て、放課後に帰る――そんな毎日。
具合悪いのが常だから、体調がいいのはうれしいことのはずなのに。
今日のこの体調の良さが、恨めしいものになってしまうなんて、思いもしなかったんだ。
『この痛みは、だれの為?』
4時間目に入る前くらいからだんだん具合が悪くなってきた。
座っていても視界がゆがんでくる。
授業の開始数分までは何とか受けることができたけど、途中で耐えきれなくなって保健室へ行くことにした。
保健室へ向かう廊下。壁に手をついて。
階段を下りるときは手すりをぎっちり掴んで。
歩きながら、ふと思う。
「今日は…彼、さぼりに来てるのかな?」
僕がいつも保健室のベッドで休んでいると、昼休みに昼寝をしにやってくる1年生の子。
たまに授業をさぼって授業時間中にもいたりするけれど。
見た目こそ…なんというかガラが悪いけど、話し相手になってくれたり、発作を起こす僕のことを心配してくれたりする、とってもいい子。
そして、僕が財閥の御曹司でも関係なく接してくれる、唯一のトモダチ。
僕は、毎日保健室にいるのが楽しくなっていた。
とん、と階段を下りて、一階の廊下。
保健室はもうすぐ。
ぺたぺたと歩く音はとても静かに廊下に響いて、何だか気持ち悪い。
それは嵐の前の静けさにも似た感覚だった。
保健室の前。
今日も先生はいないんだろうな、と思いつつ、ドアノブに手をかける。
と。
「そういう問題じゃねぇだろうが!」
保健室の中から、聞きなれた、声がした。
そう、それは、彼の性格を如実に表すような、威勢のいい、声。
だけど、その声には焦りが感じられる。
「……?」
ドアノブにかけた手が、動かない。
かぎは掛かっていないはずだけど、いよいよ具合が悪くなってきたのか、手が震える。
「……」
彼以外の声が聞きとれない大きさで聞こえた後、ばきっ、という音がした。
同時に拒否を示す声がする。
「……かな?……ないんだぞ?」
「……」
何を…話しているんだろう?
そう思った瞬間、ずき、と、胸が痛んだ。
発作?
違う、この痛みは……?
「だからこうして……」
「やめっ!――んんっ…」
「……――ほら、良い子だ」
これは本当によくない気がする。
動いて、動いて、震える手。
僕は両手でドアノブを回す。
がちゃ……。きぃっ。
開けて、入って、見たもの。
「……!」
その光景にどきりとした。
彼の上に乗っている…あれは…確か、副会長?
副会長と彼が、どうしてこんなことに?何で?
ずきっ…。
まただ。また、この痛み。
何も耳に入ってこない。
事実をどう受け入れるか、それだけに頭が働いて。
バキッ、と、いちだんと大きな音がしたときに我に帰る。
傷だらけになった彼は、副会長の下で気絶していた。
「――烏丸先輩」
「…!」
若干機嫌の悪い、低い声で副会長に名前を呼ばれる。
怖くて、おびえることしかできない僕。
「このことは、どうか――ご内密に」
シャッ、とカーテンが閉められる。
「……」
僕は、結局傷だらけの友達をを助けることすらできずに、保健室を去ることしかできなかった。
ぱたん。
保健室を出てすぐに、携帯電話を取り出して、電話をかける。
「どうかされましたか?」
「…今から早退するから、迎えに来て」
「かしこまりました」
教室に戻ってカバンを取った後、職員室の先生方に軽く挨拶をして、僕は校舎を出る。
門の前で待っていた黒塗りの高級車に僕は乗り込んだ。
「今日は体調がいいように見受けられるのですが?」
「うん。そうだったんだけどね」
ずき、と、またあの痛み。
「どんなにお具合が悪くても、放課後までいると言ってきかないのに…珍しいですね」
「なんでだろうね、本当に……」
明日からどう彼に会えばいいんだろう。
何も、知らない顔をするべきかな。
それとも、聞いてみるべきかな。
そして僕は、ずきりとしたこの痛みを、忘れることはできなかった。
PR