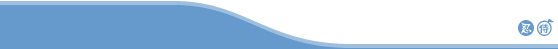今日は朝から体調が良くない気がした。
案の定1時間目でダウン。
保健室に来て、先生不在の中で体温計を取り出して測る。
37.8℃。
今日は授業範囲の勉強はやめて、昼休みまで大人しく寝てよう。
昼休み。
「開けるぞー」
いつもの声が聞こえて、うんいいよ、と答える。
いつものように昼食を食べて、談笑。
「ほんっと…お前いつ見ても顔色悪いよなー」
「そう…かな?」
「そうも何も、オレは顔色いいとこ見たことねぇ」
あぁ、よかった。いつも通り。
熱があるってこと、気付かれてない。
いつも心配されてるし、これ以上変に心配されたくないもの。
「で、薬は?」
「飲まない」
僕はにこにこして答える。
彼の顔を見る限りだと…そうだな、イライラという言葉がしっくりくるかも。
「……だから何で飲まねぇんだよ薬!!」
彼はそう言ってばふっと毛布に手をたたきつける。
やだなぁ。理由くらいわかってるはずだよね?
「嫌だから」
「嫌だとかそういう問題じゃねぇ!!」
「だってー」
「だってじぇねぇ!!」
こんな量の薬、見るだけで嫌になる。
ここまで量が多いと、飲む時間まで考えないと薬の副作用で死に至ったりすることもある。
薬を飲むときも死と隣り合わせなんて、そんなの嫌。
それに、薬を一回飲まなかったからって、どうってことないんだ。
ちょっとしんどくなるだけ。僕が我慢すれば平気。
確かに「ちょっとしんどい」のがずっと続けば確かに死んじゃうかもしれないけど…
僕の身体が弱いせいで、烏丸財閥の後継者争いが起こってる家庭内の状況から抜け出すことができるなら、それでも構わない。
そのうち、僕は後ろからドスやハジキで殺されてしまいそうだもの。
だから、僕の心配なんて、しないで?
そんなに心配するなら……困らせて何も言えないようにしてあげる。
「じゃあ…キミが飲ませてよ」
満面の笑みを浮かべる。
「ほぉーお?」
じゃら、と薬を持って今にも僕の口に押し込めそうな彼。
それはやめてよ。苦しいから。
「そうじゃなくて、もっと優しい感じがいい」
どんな方法かは僕には思いつかないけど、口に押し込めるのよりかはもっとましな方法があるはずだ。
僕に思いつかないから、キミにも思いつかないよね?
「はぁ?意味わかんねぇよ。そこまで言うなら自分で飲めよ」
「やだ」
そういって僕はベッドにもぐりこむ。
「キミがいい方法思いついてやってくれなきゃ飲まない」
こほ、と軽く咳をする。
ほら、思いつかないでしょ。だからさ。
もう勝手にしろ、って言って保健室出ていってくれたら、ちょっと寂しいけど、それでも構わないや。
僕がこうやってわがまま言ってること、キミは大迷惑だっていうの、僕は知ってるから。
迷惑な奴に関わらなくて済むんだよ?違う?
沈黙が、続く。
だけど、まだ彼はそばにいる。
何考えてるんだろう?僕にはわからないけど。
「――おい」
呼ぶ声がした。
反射的に僕は起き上がる。
「何かいい方法思いつい――」
彼の手が僕の肩を掴んだ。
「た……?」
少しかさついた感覚が僕の唇に触れる。
紡ごうとした言葉は塞がれた。
「――ん…っ」
何が何だかわけのわからない僕。
ちょっと苦しくて毛布をきゅ、と握る。
ぎし、と、ベッドがきしむ。
「んくっ……ふ…」
するりと舌が滑り込んできて、歯列をなぞって僕の口を開けると、無味の液体が流れ込んできた。
それと一緒に、粒やらカプセルやら、薬も流れ込んでくる。
流れ込んできた薬を、こく、と、飲みこむ。
それを確認したかのように、ふさがれた唇は解放される。
「――・・・・・・」
「…はぁっ……」
「……」
熱る顔。上がる息。
唇は解放されても、まだ肩は掴まれたまま。
「……今…何、を……」
こうは言うけれど、何されたかくらいは分かってる。
「……“キミが飲ませてよ”って言ったのはてめーだろ?」
「それは……」
顔が近い。
やっと肩も解放されたけど、直視、できない。
「そう、だけど……」
まさかこう来るとは思わなかった。
不思議といやな気はしなかったけれども。
「それにお前、熱あんじゃねーか」
「……!」
額に手を当てられて、僕は思わずびくっとする。
――気付かれた。
「だ、大丈夫だよこれくらい――!」
手を振り払って気にしないふり。
「――……心配なんだよ」
「――え?」
ぼそりとつぶやく声。
僕はそれを聞き取れずに。
「いーや、何でも」
とん、と彼はベッドから降りて。
「これに懲りたら二度とわがまま言うんじゃねーよ、ばーか」
べ、と舌を出して言う。
シャッ、とカーテンが閉まった。
「うん……」
一応こうは返すけど。
「たぶん、ね」
まだ熱の残る唇に触れて、つぶやいた。
PR