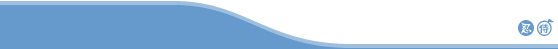満月の夜、ダイヤモンドダストの降る樹海。
空に浮かぶは血飛沫。
同時に、どさどさ、という複数の音。
「……もう、来ないよね?」
少し息を切らせつつ、少女は足もとに目をやる。
瀕死にはなっているものの、まだ息はある、元同胞。
それと、一族を目の敵とする、憎き天敵。
満月の夜は、少女を狂わせた。
それは、その美しさ故か、神秘的な月光の力か。
本当は、こんなことをするのは嫌いなのに――彼女は満月を迎えるたびに思う。
ふ、と辺りが暗くなる。
明るく道を照らしていた月が、隠れる。
手にする鉤爪には肉片と血が付着している。
少女はひと振りして付着物を払い落とした。
その姿は、冷酷非道の暗殺者そのもの。
彼女の持つ鉤爪は、昔々、暗殺の技術を身につけさせられた時からずっと使っているものであった。
そして、暗殺の技術とともに教わったこと、それは――
「!」
遠くで雪を踏みしめる、何かが近づく音。
少女は身構えて、様子を伺う。
「――お、なんだ、お前かよ。こんなところで何やって……」
「――!」
木の蔭から出てきたのは、いつも優しくしてくれる、想い人。
彼女の脳は瞬時にものを考え始めた。
何で?
どうしてこの時間にこんなところに?
そんなことよりも、見られてしまった。
見られてしまった。
見られてしまった。大好きな、あの人に。
怖い。
怖い。
嫌われるのが、叩かれるのが、怖い。
――もしもその姿を見られたならば、対象を殺しなさい。決して自分が死ぬことは許されないのです――
「こ…来ないで…ください……」
来たら、私は貴方を殺さなければならないから。
言うことができず、少女の精いっぱいの抵抗は夜の闇に吸いこまれる。
「って…血ぃ付いてんじゃねぇか…いったい何が…っ」
近づこうとする少年に向かい、反射的に動く少女の体。
しゅっ、と鋭く風を切る音がして、夜空に舞う、鮮血。
「痛ー……何しやがんだ!」
「……ご、ごめ、なさ…」
声を聞いて少女は我に帰る。
「謝るならするんじゃねぇ!」
「――っ」
再び我を忘れ素早い身のこなしで攻撃を繰り出す。
抵抗しようと少年は拳を上げて、
―ご、ごめんなさ……何でも、するから……たたかないでっ…!!―
―…叩かねぇっつの…―
初対面の時の怯えきった顔を思い出して、止まる。
「(殴れねぇ……)」
素早さならば若干こちらの方が上で、避けることはたやすくはないができないわけではない。
しかし、防ぎ、避けるのだけではらちが明かない。
そうこうしているうちにも傷は増えていく。
「…ちくしょー……どーすりゃいーんだこれ…」
暗闇に未だ目は慣れず、なぜ戦いを好まない彼女が、それも自分に向かって攻撃してくるのかが理解できない。
幸か不幸か、ふ、と、雲が晴れ、満月が夜道を照らし始めた。
ダイヤモンドダストが月光を反射し、きらきらと降り注ぐ。
「これでなんとか……」
少年は対峙する少女を見据えた。
「……?」
見据えた先の少女は、たくさんの返り血を浴びながら、自身にも傷を負いながら立っていた。
おそらく自分に会う前につけられた血と傷だろう。
そう思い、どうやって傷を付けずにこの場を収めるかを考える。
しゅん、と、一瞬で姿が掻き消え、次に目にするは至近距離の少女の顔。
「……泣いて…」
寸前で攻撃をかわして間合いを取る。
再び見据えた先で、――少女は泣いていた。
ぽろぽろとこぼれる涙は、自分を解放してといわんばかりに訴えかける。
「泣くぐらいなら…こんなことすんじゃねぇよ……!」
聞こえてるのか聞こえてないのかはわからない。
だけれども。
振り下ろされる少女の右腕をつかみ、引きよせた。
ぎゅっ、と、抱きしめる。
「……っ!」
少女の左手の鉤爪が肩をかすめ、鋭い痛みが走った。
それでも、離さずに。
「……オレは、お前だったら殴らねぇから…いつまでも怖がってんじゃねぇよ」
すると、ふわ、と少女の体から力が抜けた。
同時に涙もすぅ、とひいていく。
瞳に光が戻る。
「ぁ……ご、ごめ…なさ……」
正気に戻って自分の体の疲労がピークに達したことが理解でき、少女はふらりと倒れこむ。
少女を背負い少年は夜の森を歩いて行った。
「わ、どうしたのその傷!」
「……オレより…こいつを」
背負っていた少女を下ろし、少年も倒れこんだ。
半日後。
――何だこの感覚…やわらかくて…温かい……
ぱち。
「ぅ……」
ぼやりとした視界。戻る感覚。
不思議な感覚は、手からのものだった。
感覚のある方へ目をやると、そこには白い手袋をはめた少女の姿。
自分の手を握ったまま、椅子に座って寝ているようだった。
目の前にある時計の時刻は午後1時。
昼寝にちょうどいい時間だった。
少年はまだ若干痛む体を無理やり起こす。
「ん……」
それに気づいたのか、少女も目を覚ました。
そして、少年と目を合わすや否や、ぱっ、と手を離し、怯えた表情で少年を見る。
「お前……」
「ぅ……あの……」
少女は今にも泣きそうだった。
「…昨日…オレは何も見てないし、お前は何にもやってねー。それでいいだろ?」
「……っ!」
「忘れろ忘れろ!な!ハイ忘れた!オレは何も知らねーからな」
今にも崩れそうだった彼女の顔が、きょとんとし、微笑みへと変わる。
それを見て、少年はがしがしと少女の頭を荒っぽく撫でてやった。
続かないのでここでおしまいwwwww
何かもう…いろいろとごめんね!>私信
PR