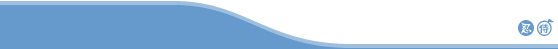みんなのところに顔を出さずに女子部屋に戻った。
誰もいないから鍵をかけて、ベッドに入って丸くなる。
「マヤやん、晩御飯はー?」
エミュんがドアの向こうから聞いてくる。
「……いらない」
「じゃあ冷蔵庫に入れとくから、お腹減ったら食べてね」
「……うん」
それだけ返事をして、もっと丸くなる。
ご飯なんていらない。食べたい気分じゃない。
こんな顔でみんなに会ったら心配されちゃう。
今日のお昼のこと。
考えるだけで涙が出てくる。
どうしよう。
どうしよう、どうしよう。
嫌われちゃったかな、あんなこと言って。
頭の中をぐるぐると、ぐちゃぐちゃと。
私のこと、すきじゃなかったのかな。
やっぱり舞い上がってただけなのかな。
馬鹿みたい。馬鹿みたい。
泣いちゃって、馬鹿みたい。
いきなり泣いちゃって、迷惑だっただろうな。
彼の手を振り払ったときに触れた右手が、痛い。
物理的な痛みじゃない。罪悪感を感じるこの右手を、切り落としてしまいたい。
ぎゅ、と目をつぶると、昼間流れた涙の残りがあふれてくるようだった。
こんこん。
ぐちゃぐちゃの思考の中で鮮明に聞こえる、ドアをノックする音。
「……?」
「マヤやん、あたしだけど……開けていい?取りたいものがあるんだけど」
「姐さん……?……いいよ」
「ありがと」
がちゃん、と錠が開く音がして、かちゃ、とドアの開く音。
かちゃ、と閉まって、がちゃん、と錠が落ちた。
カツカツカツ、とヒールの音が近づいてくる。
あれ?姐さんのベッドは部屋の一番手前じゃなかった?
「隣、座るね」
姐さんはそれだけ言って、私のベッドに腰かけた…みたい。
ぎっ、と軋む音がして、かつ、かつ、とヒールの音。
脚、組んだのかな。
「部屋真っ暗にしちゃって……泣いてるでしょ」
「えっ……?」
背中を向けてるはずなのに、コイコ姐さんにはお見通し。
ぴた、と頬を撫でる感覚がして、
「やっぱり。涙の跡ついてる」
そう言った。
少し顔を上げると、姐さんが困ったような顔をして笑ってる。
月明かりに反射した雪の光が、姐さんの髪を照らしてる。
青い海のような髪の毛は、キラキラしてて季節外れの天の川みたい。
姐さんは私の前髪を梳きながら、
「泣いてる所を見せたくないときは部屋を暗くするのが一番よねー……彼氏さんとなんかあった?」
やさしい声色で言った。
恋愛事には疎いって自分で言ってるくせに、こういうのには目敏いんだから。
私が軽く頷くと、姐さんはしょうがないな、といった感じでくすくす笑った。
「そっかそっか…みんなに話すと彼氏さんの命が危ないもんね」
一度泣いて帰ったとき、みんなが怒って彼のところに乗り込んだことがあった。
次の日に会ったとき彼は傷だらけで、どうしたんですかって聞いたらなんでもねーって返された。
誰かと喧嘩でもしたのかな、って思って、怖いなってその時は思ったけれど。
ワーちんから話を聞いた時は本当に申し訳ない気持ちでいっぱいだった。
「でも、こうしてひとりで泣いてたって解決なんてしないわよ?よければあたしに話してみない?」
布団の中から姐さんを見る。
どうすればいいかわからない私にとって、姐さんは女神にすら見えた。
深呼吸して、昨日のことを思い出す。
思い出したくはないけれど。
「……あのひとが、」
出てきた声は掠れていて。
泣き疲れてるってことを体が訴えているようだった。
「キス…してるの、見た」
「…そう…誰と?」
姐さんは淡々と聞いてくる。
「きれいな…ゴウカザルの女のひと」
「それで、マヤやんはどうしたの?」
「走って、逃げた……昨日の、話…」
「そう。じゃ、キス終わった後は見てないんだ?」
「……うん」
私の答えを聞いて、姐さんは少し考え込んだ。
しばらくして、んー、という声が聞こえて、
「それで、マヤやんは…二人を見てどう思ったの?」
どきりとする一言を言い放った。
どうって…どうって言われても……。
「……彼氏と、彼女…」
そうとしか思えなくて。
それ以外の何でもなくて。
私なんかよりも……ずっと、お似合いで。
「何で自分が彼女なのに、その女の人を彼女って思ったの?」
「だって、私なんかより…ずっときれいで、」
「そんなのマヤやんの一方的な主観じゃない」
さっきまでとは打って変わって、冷たく放たれた一言。
部屋に、びぃんと響き渡って、壁に吸い込まれる。
「もっと自信持ちな。彼氏さんはマヤやんがタイプなんじゃないの?だから付き合ってるんでしょ?」
がつがつというたとえが合うような口調で、姐さんは言う。
そんなこと思ってもなかったから、私は目を丸くするだけで。
「あたしは全然こういうのは分かんないけど…そうなんじゃないの?」
髪をかきあげて、はー、とため息をつく姐さん。
同時に脚も組みかえて、きれいで長い脚が惜しげもなく晒されて。
あぁうらやましい、こんな色気が私にもほしい…なんて思う。
「それと、一つ言わせてもらうけど、マヤやんが何も言わないから彼氏さんも不安なんじゃない?」
「……!」
一番、気にしてたこと。
やっぱり周りから見てもそうだったんだ。
「マヤやんがはっきりしないから…他の女に関心が向いたりとかするんじゃないかしら」
ま、男心なんてわかんないけど、と軽く首をかしげる姐さん。
考えてみれば、今日…泣きながら叫んだあの言葉以外で、私は彼の名前を呼んだことがない。
今日以外に、すきって伝えたこともない。
すきって言われた時も、どうすればいいかわからなくてただ頷いただけ。
「……」
「んー、こっから先はあたしの管轄外ね。もっと恋愛のエキスパートに聞いた方がいいかもね」
姐さんは肩をすくめて、軽く微笑んだ後スッと立ち上がって。
「じゃ、あたしはひとっ風呂浴びてこようかなー」
じゃあね、と言ってカツカツと歩き出して、かちゃん、とドアが閉まった。
鍵はかけてないみたい。
静けさが支配する部屋で、私はもう一度布団に入る。
そういえば、どうして私はあのひとのことが好きなんだっけ。
いつも優しくしてくれるから?
コンテストですごいパフォーマンスを見せるから?
一緒にお昼寝してくれるから?
……私のこと、たたいたりしないから?
全部はずれ?全部あたり?
……でも、ひとつだけ言えるのは。
一緒にいて、笑っていられるから。
いろいろ話したり考えたりしたら…お腹減ったな。
ドアの向こうから、声がする。
「マヤやん大丈夫だった?」
「んー……笑ってくれなかったけど…たぶん大丈夫。ご飯持ってってあげて、話聞いてあげて?」
「わかった」
しばらくして。
こんこん。
二回目のドアノック。
「マヤやーん。お腹減ってない?入っていい?」
トワちゃんだ。
「…うん、いいよ」
返事をすると、かちゃ、とドアが開く。
「ご飯。食べる?」
お盆に乗ったご飯を少し持ち上げて、トワちゃんは言った。
「……うん」
私は起き上がって、少し歩いて部屋の中央にあるテーブルに座る。
今日のご飯はカレーライス。いいにおいが漂っている。
そんなに熱くしていないカレー。猫舌の私に対する配慮。
「電気つける?」
「大丈夫。……いただきます」
トワちゃんは私の向かいに座って、食べる様子を見ている。
「男って、行動で示してもらいたい生き物らしいよ?」
「なっ…何?いきなり」
「男ってみんなそう。見ててそう思う」
そっか、トワちゃんいっつも男の人からかってるもんね。
「ちゅーのひとつやふたつやれば相手も安心すると思うけど……マヤやんも今、不安なんでしょ?」
「……うん」
「でも、今日何か言ったでしょ」
トワちゃんの大きな紫の目が、不敵に細まる。
これは見透かされてる。
さすがエスパータイプ。すごいなぁ。
「……勢いで…すきって、言った」
「じゃあどうして今こんな状況なの?」
「……私、気持ち、押しつけた」
「押し付ける?何で?」
「返事、聞かなかったから」
「ふぅん……」
ふむ、とトワちゃんは考えて、ニコッと笑った。
「マヤやん頑張ったね」
「……え」
「よく自分の気持ち、伝えたね」
「……でも、」
「このまま別れるかもって?別れたっていいじゃん。それでも、気持ちを伝えるっていうのは大切。違う?」
「よく、わかんない、けど」
カレーを口へ運んで、ぱくりと食べる。
ちょっと辛いな。誰作ったんだろう…ワーちんかな。
「んー…今はわかんなくていいんじゃない?」
「どうして?」
「気持ちを伝えるっていうのは、言い換えると相手が自分の気持ちを知るってことでしょ?」
「うん」
「あいつはマヤやんの気持ちを知って、何か考えてるかもしれないよ」
「……!」
かまずにカレーを飲み込んで、のどに詰まらせる。
手元の水を飲んで、流し込む。
…どきどきした。
勢いで言ったことについて、考えてるかもしれない?
どう思ってるのかな、何考えてるのかな?
「気になってるでしょ」
「えっ…そ、そんなこと」
「気になってるなら、僕がとっておきの方法教えてあげる」
「?」
「ちょっと耳かして」
トワちゃんに耳をかす。
「あのね……」
「……!?」
すべて聞き終わった後、あまりの恥ずかしさにすぐに耳を押さえてトワちゃんから距離をとった。
「とっ……トワちゃん…それは無理……っ!」
「事実さえ作れば…まぁ、マヤやんにはムリだよねー」
「そ、それ以外で方法はないの…っ?」
「それはマヤやんが自分で決めてやるべきだよ」
ぱちん、とウィンクしてトワちゃんは話を続ける。
「そうだな、マヤやんが今すんごい不安だったら…相手に行動を起こしてもらうのもありだよね」
「行動……?」
「そ、行動。マヤやんが安心できるようなことを、相手にしてもらうの」
「安心、できるような……」
「相手に行動を起こしてもらうんだから、マヤやんは一言きっかけになるようなことを言えばいいだけ。それを言う勇気を持てばおっけー」
「そっか……考えてみるね」
ちょっぴり安心して、自然に笑みがこぼれる。
「よかったー笑ってくれて。姐さんから話聞いたとき、笑わなかったって言ってたからどうしようかと思ったよ」
「……?」
「マヤやんが笑ってないとみんな心配なの。ほら、ワーちんが王子様王子様言ってなかったり、エミュんが走る練習してなかったり、姐さんがしおらしかったり、テンちゃんが悪戯してなかったりしたら、心配でしょ?」
「うん…それにトワちゃんが男の人からかってなくても心配だね」
「それと一緒。マヤやんは笑ってないと、ね?」
「……」
「それじゃ、僕そろそろ寝るね。どうも夜は苦手なんだよねー。あ、全部食べた?皿持ってくね」
「ありがとう」
ふぁ、とトワちゃんはあくびをして椅子から立ち上がる。
「それじゃ、おやすみ」
「おやすみ」
かちゃん。ドアが閉まった。
「……笑ってないと…かぁ」
トワちゃんは、私が笑ってないと心配って言ってたけど……あなたはどうなのかな?
私は笑ってた方が、いいのかな?
泣いちゃって、心配かけたかな?
だったら、ごめんなさい。
私はあなたのことが、大好き。
だから、私のこと…嫌いになって、ないといいな。
もしも会うことが許されるなら…勇気を出して一言、言ってみるの。
また、あなたの前で笑いたいから。
PR